|
哲学専修課程へ戻る / 文学部トップへ戻る / インド哲学仏教学専修課程へ
中国思想文化学
中国文化は、4000年前に誕生した古代文化が変容しつつ連綿と継続し、現在もなお発展を続けているという点で、世界の他の文化にはない際立った特色を持つ。中国思想文化学専修課程が取り扱うのは、この4000年にわたる中国文化の展開を支えた人間の知の営みの軌跡にほかならない。
中国の思想文化は時間軸に長いだけでなく、学問的にも地理的にも広い範囲にわたる。学問分野で言うと、狭義の哲学のみならず、政治思想、経済思想、科学思想、軍事思想などなど、人間と社会と自然の在り方をめぐる中国人の思惟に関するさまざまな分野が含まれる。さらに、中国文化は日本や朝鮮(韓国)などの周辺諸国に大きな影響を及ぼしてきたから、東アジアの文化比較や文化交流も本専修課程が取り扱う対象に含まれることになる。
1) カリキュラム
授業は講義と演習とからなる。講義は「中国思想文化学概論」「中国思想文化史概説」「中国思想文化学特殊講義」の3種類。「中国思想文化学概論」は中国思想を学ぶ上で基礎になる事項についての見取り図を提供するもので、具体的には経学と科学について開講している。「中国思想文化史概説」は、古代・中世・近世・近現代という時代別に構成された中国思想文化の歴史で、2年間の在籍期間中に全ての時代についての講義を履修できるように制度設計してある。また「中国思想文化学特殊講義」は、学問の最前線に立つ研究者が自分の専攻する分野について立ち入った講義をするもので、在籍する学生の需要に合わせて講師を選択することも多い。
演習は、講義以上に重視している訓練の場である。所属する専任全教員が学部演習を持ち、学生は必ずいずれかの演習(多くの場合は複数)に参加し、テキスト読解能力を鍛えられる。
2) 勉学環境
専修課程の共同研究室は、2003年に全面改築されたばかりの赤門地区総合研究棟7階にあり、学部学生もリファレンス・ツールの完備するこの明るく広々とした部屋を拠点にして、自由に勉強することができる。共同研究室のパソコン群には、『四庫全書』のデータベースが収められているから、学生は中国史上最大の叢書である『四庫全書』を、あたかも自分の蔵書であるかのように利用することが可能である。このほかにも、近年陸続と作成されている各種データベースをその都度購入している。
一方、書籍のかたちを持つ史料群のほうは、東京大学文学部所蔵の漢籍を一括収蔵する文学部漢籍コーナーとして同じ建物の6階にあり、演習の準備やレポート・論文の作成に日常的に役立っている。また、日本国内屈指の漢籍所蔵数を誇る東京大学東洋文化研究所図書室は研究室から徒歩わずか2分の位置にある。このほか、史学研究や近代研究方面で多くの貴重な書籍を蔵する東洋文庫は地下鉄で2駅の駒込に、江戸時代の幕府の蔵書の多くを引き継ぐ国立公文書館内閣文庫も20分で行ける竹橋にあるから、中国を研究する学生にとっては、文献利用の点でも日本で最も恵まれた環境である。
|
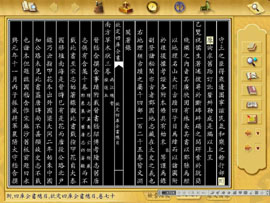
共同研究室 四庫全書のデータベース
|
|

赤門地区総合研究棟6階 文学部漢籍コーナー
|
3) 卒業論文
中国思想文化学専修課程の学生は卒業論文を書いて卒業することになるが、学生自身の問題関心を最優先にするから、卒論のテーマはきわめて多様で、狭義の思想関係のほか、食物文化や言語の問題をあつかったものもある。研究室の規模は小さいが、その分、風通しがいいため、大学院生と学部学生の関係が密接で、卒論の準備に際して、教員だけではなく、大学院生もアドバイスを与えることが珍しくない。
4) 卒業後の進路
年度によって異なるものの、概して言えば、大学院に進学する者と社会に出る者がほぼ半数ずつである。大学院進学者の大部分は、博士課程を修了して大学教員となることを目指す。社会に出る者の就職先は多様で一概に言えないが、外務省に就職して中国専門家になった者もいる。また、研究者になることとも、会社員や公務員になることとも異なる第3の道、すなわち法科大学院や公共政策大学院に進学して高度専門職業人になることを目指す学生が出てきている。今後日本と中国との関係がさらに拡大することは確実だが、関係の拡大はまた不可避的にトラブルを発生させることになる。そうした時、交渉を担当する政策立案者や渉外弁護士が相手国の文化に対する十分な理解を持つことはトラブル解決のために不可欠で、本専修課程で中国思想文化に関する十分な知識と高度な中国語能力を身につけた学生こそ、そのような人材に育つ最短距離にいると言えよう。
▲ このページのTOPへ
哲学専修課程へ戻る / 文学部トップへ戻る / インド哲学仏教学専修課程へ
|