|
|
|
中国思想文化学専修課程へ戻る / 文学部トップへ戻る / 倫理学専修課程へ
インド哲学仏教学
インドの思想文化は、3000年にわたる長い歴史を通じて、その豊かさと奥深さをもって、アジアはもちろん、西欧の人々をも魅了しつづけてきた。インドは7回生まれ変わっても学びきれないと言われるほど豊かな内容をもつ『ヴェーダ』をはじめ、多様な哲学的・宗教的な文化・文献を蓄積してきている。また、インドからアジア各地に広まった仏教は、東南アジアや東アジア、またチベットにおいて、今日でもなお力強い生命を保ち、多くの人々の生きる指針となっている。永遠に新しく、汲めど尽くせぬこの豊かな思想文化の伝統の一端にでも触れることは、我々に大きな勇気と慰めを与えてくれる。
インド哲学仏教学専修課程(略称印哲)は、このようなインドの思想文化、およびインドに起源をもち、アジアの諸地域に展開した仏教の思想文化の研究と教育を目的とする。その研究対象は、インドの古代から近代の思想文化にまで及び、また、仏教に関しては、インドだけでなく、東南アジア・チベット・東アジア(中国・朝鮮・日本)の仏教も含む。このようにきわめて広い研究領域をもつことは、本専修課程の特徴であり、大きな魅力の一つである。
インド思想にしても仏教にしても、長い歴史と生活の隅々にまで及ぶ幅広い影響力をもつから、その研究方法は多様であり、歴史学・考古学・人類学あるいは比較思想などからのさまざまな切り込みも可能である。 しかし、その基礎となるのは文献の研究である。しっかりと正しく文献を読む力を身に付けておかないと、浅い理解で終わったり、とんでもない誤解に陥らないとも限らない。それゆえ、本専修課程では原典による文献研究に重点を置き、その基礎力の養成を大きな目標とする。一見、これは迂遠に見えるかもしれないが、巨大な対象に向かうには、それだけ周到な準備が必要なのである。 しかし、その基礎となるのは文献の研究である。しっかりと正しく文献を読む力を身に付けておかないと、浅い理解で終わったり、とんでもない誤解に陥らないとも限らない。それゆえ、本専修課程では原典による文献研究に重点を置き、その基礎力の養成を大きな目標とする。一見、これは迂遠に見えるかもしれないが、巨大な対象に向かうには、それだけ周到な準備が必要なのである。
ところで、原典を読みこなすために何よりも必要なのは語学力である。インドにはきわめて多数の言語があるが、主要な哲学文献はサンスクリット語で書かれている。それゆえ、本専修課程ではサンスクリット語を必修として、その基礎力の養成に力を入れている。たとえ中国や日本の仏教を専攻しようという人でも、仏教がインドから伝わったものである以上、まずサンスクリット語を学んでその原点を把握することが要請される。その上で、必要に応じて、パーリ語・チベット語・ヒンディー語・中国語など、さまざまな言語を学ぶ必要がある。哲学・宗教を学ぶつもりで来たのに、語学ばかりというぼやきも出るかもしれないが、そんなことはない。基礎さえしっかりできれば、そこから無限の世界が広がってくるのである。
このようなわけで、本専修課程に進学を希望する学生は、教養課程で哲学的なものの考え方に習熟することはもちろんであるが、あわせて諸外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語など)をできるだけ身につけておいてほしい。また、サンスクリット語文法は本郷でも開講されているが、なるべく駒場で学んでおいてほしい。
本専修課程は、明治43年(1910)に遡る長い歴史をもっている。しかし、単に古い伝統を誇るだけでなく、常に新しい問題意識をもって日本の、ひいては世界の学界・思想界に大きな貢献をなしてきた。専修課程の名称として、長い間、創設以来の「印度哲学」を用いてきたが、平成6年(1994)より「インド哲学仏教学」に改められた。それによって本専修課程の内容はより明瞭になったと思われる。
本専修課程の必修単位は44単位で、インド哲学概論・インド哲学史概説・仏教概論・比較仏教論から8単位、サンスクリット語文法4単位、特殊講義12単位、演習8単位、及び卒業論文または特別演習12単位である。その他、選択が40単位で、計84単位が卒業のために必要な単位である。単位取得に当って、例えば、教養課程でサンスクリット語文法を終えた学生は、改めてその授業を取らず、サンスクリット語を用いた演習によって代用できるなど、意欲ある学生のためにさまざまな配慮がなされている。なお、言語文化学科のインド語インド文学専修課程は本専修課程と関係が深く、そこで開講されるサンスクリット語やパーリ語などの講義もできるだけ聴講してほしい。その単位は本専修課程の特殊講義の単位にあてることができる。また、「外国語」として開講されているチベット語も、研究の進展のためにはぜひ聴講してほしい。
本専修課程では、卒業に当って、卒業論文よりも特別演習を取る学生が多い。特別演習は、あらかじめ定められたサンスクリット語文献(『ウパデーシャ・サーハスリー』など)や漢文文献(『大乗起信論』など)のうち、3種を選んで自習し、学年末に試験を受けて、その成果を判定されるものである(各4単位)。大学院に進学する学生の場合、特別演習で基礎力をしっかりと身につけておき、進学後、修士論文に全力投球するというのが、多く見られるパターンである。とはいえ、もちろん卒業論文に挑戦するのも大いに結構なことである。
本専修課程は、教養学部から進学する学生のほかに、他専修課程、他学部、あるいは他大学を卒業してから学士入学する学生もいて、ヴァラエティーに富んでいる。 卒業後は大学院に進学する学生が多いが、教職や一般企業に就職する学生も増えている。大学院はインド語インド文学専修課程と共同で、インド文学・インド哲学・仏教学専門分野を組織している。そこには優秀な先輩たちが多くいて、よいアドヴァイスを与えてくれるであろう。また、大学院には、外国からの留学生も多く、国際色が豊かである。 卒業後は大学院に進学する学生が多いが、教職や一般企業に就職する学生も増えている。大学院はインド語インド文学専修課程と共同で、インド文学・インド哲学・仏教学専門分野を組織している。そこには優秀な先輩たちが多くいて、よいアドヴァイスを与えてくれるであろう。また、大学院には、外国からの留学生も多く、国際色が豊かである。
最近、以前より学生数が増加してきているが、学生同士、あるいは教員と学生の関係は緊密である。毎年春には新入生歓迎会として、著名寺院の見学などを含む一泊旅行を行ない、また、年に数回の研究例会では、先輩たちの意欲に満ちた研究発表を聞くこともできる。
あらゆる面で昏迷の深い現代だからこそ、もう一度、人間精神の根本に立ち返り、インド思想や仏教の哲人たちの奥深いことばに静かに耳を傾けてみようではないか。
▲ このページのTOPへ
中国思想文化学専修課程へ戻る / 文学部トップへ戻る / 倫理学専修課程へ
|
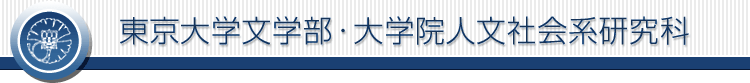
 しかし、その基礎となるのは文献の研究である。しっかりと正しく文献を読む力を身に付けておかないと、浅い理解で終わったり、とんでもない誤解に陥らないとも限らない。それゆえ、本専修課程では原典による文献研究に重点を置き、その基礎力の養成を大きな目標とする。一見、これは迂遠に見えるかもしれないが、巨大な対象に向かうには、それだけ周到な準備が必要なのである。
しかし、その基礎となるのは文献の研究である。しっかりと正しく文献を読む力を身に付けておかないと、浅い理解で終わったり、とんでもない誤解に陥らないとも限らない。それゆえ、本専修課程では原典による文献研究に重点を置き、その基礎力の養成を大きな目標とする。一見、これは迂遠に見えるかもしれないが、巨大な対象に向かうには、それだけ周到な準備が必要なのである。 卒業後は大学院に進学する学生が多いが、教職や一般企業に就職する学生も増えている。大学院は
卒業後は大学院に進学する学生が多いが、教職や一般企業に就職する学生も増えている。大学院は