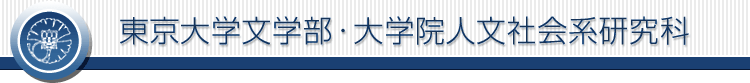|
イスラム学専修課程へ戻る / 文学部トップへ戻る / 東洋史学専修課程へ
日本史学
(1)日本史学の特質
日本史学は、日本列島およびその周辺の過去の歴史過程について、多様な側面から総合的に考究しようとする専門分野である。研究の基礎は、古文書・記録・史書・年代記などの文献史料を、正確に読み、内容を批判的に検討し、そこから歴史上の固有の論点を引き出して、あらたな歴史像を構成することにおかれる。したがって、当研究室の教育・研究システムも、そうした力量を養成することを中心に組み立てられている。
演習では、各時代の歴史理解にとって不可欠の文献史料を原文に即して解読する、あるいは、それらの史料を使って書かれた先学の優れた論文を批判的に検討する、といったことが中心的な内容となる(外国語で書かれたものを含む)。講義では、各教員の行っている先端的な研究の内容をかみくだいて話すことになるが、その場合でも、<史料をしていかに歴史を語らせるか>を軸とする講義が多い。
一方、近年、日本史学の対象とする史料は、文献のみではなく、絵画や文学を始めとする芸術作品、発掘調査の成果である遺跡や遺物、習俗や民俗行事、地図や地名などへと、広がりをみせている。むろん専門的には、美術史学・国文学・考古学・民俗学・建築史学・歴史地理学などの諸領域があるが、日本史学の側からも、これらの史料を再検討し、新たな問題提起を行うようになってきた。
当研究室の学生も、文献史料に対する専門性をしっかり踏まえた上で、そこに閉じこもらずに、できる限り広範な対象を史料として取り上げる姿勢が望まれる。
(2)教員の自己紹介
現在の当研究室の専任教員は6名、助教1名である。時代ごとの専門性を考慮して、古代・中世・近世・近現代に2名ずつという構成であったが、現在は中世・近世が1名となっている。時代区分はあくまでも便宜的なものであり、時代の枠を超えて積極的に発言しあう気風がある。
佐藤 信は、古代史を専攻している。多様な歴史資料の検討を通して日本列島の古代史の総合的な再構成をめざしている。とくに、古代国家の中央集権性、木簡や出土文字資料、古代都市の実像、そして史跡調査などを研究対象とする。著書に『日本古代の宮都と木簡』(吉川弘文館)、『出土史料の古代史』(東大出版会)、『日本の時代史4 律令国家と天平文化』(編著、吉川弘文館)、『古代の地方官衙と社会』(山川出版社)など。講義では、文献資料のみでなく出土文字資料や遺跡などの検討の上に古代社会の実像にせまる。演習では、古代の基本史料である六国史の正確な読解をめざす。また、史跡・史料の現地調査を行なう。
野島(加藤)陽子は、近代政治史を専攻する。外交と軍事、2つの側面から昭和戦前期の特質について考えている。著書に『模索する1930年代-日米関係と陸軍中堅層』(山川出版社)、『徴兵制と近代日本』(吉川弘文館)、『満州事変から日中戦争へ』(岩波新書)、『天皇の歴史08 昭和天皇と戦争の世紀』(講談社)がある。なお論文を著す時には旧姓加藤を使用しているのでご留意願いたい。講義では、近代の政治・外交上の一次史料を中心とした文書・記録を読み解き、日露戦争から太平洋戦争までの外交史と近代の天皇制についてを論ずる。演習では、昭和戦前期の史料を講読するほか、学生による報告もおこなっている。
大津 透は、7世紀から12世紀の国制史を専攻するが、吐魯番文書の分析を通じて唐代史にも関心をもっている。天皇制や国家財政を中心に律令制の検討を続けているが、従来検討の遅れていた古記録の分析による摂関期の国制、法のあり方の解明にも力をいれている。著書に『律令国家支配構造の研究』(岩波書店)、『古代の天皇制』(岩波書店)、『日本の歴史06 道長と宮廷社会』(講談社)、『古代史を学ぶ』(岩波書店)、『天皇の歴史01 神話から歴史へ』(講談社)、『律令制とはなにか』(山川出版社)、『日唐律令制の財政構造』(岩波書店)がある。講義では古代法の特質から国家構造を検討し、演習では平安貴族の日常を語る摂関期の史料を正確に読む。
鈴木 淳は、明治期の社会経済史が専門である。まとまった研究としては日本における機械工業の生成過程とその意味を、民間中小工場を重視して検討し、課程博士論文とした。これは『明治の機械工業』(ミネルヴァ書房)として刊行されている。その後、機械を中心とした新技術の導入、活用を軸として日本近代史を展望しようと試みており、東京の消防の近代化を扱った『町火消たちの近代』(吉川弘文館、歴史文化ライブラリー)、駒場での授業内容を基にした『日本の近代15 新技術の社会史』(中央公論新社)、『日本の歴史20 維新の構想と展開』(講談社)を執筆した。演習では、夏学期に論文を読んで日本史の学術論文のあり方を学び、冬学期には学生が史料に基づいた研究発表をする。
牧原 成征は、日本近世史を専攻している。これまでは、信州・近江・関東等の村落構造や土地制度を中心に、商人や流通・交通・金融、かわた等の身分とその集団などを検討してきたほか、中世から近世にかけての社会の変容を、土地・身分政策に即して論じてきた。今後はそれらをふまえて、幕府や江戸、藩や城下町についても少しずつ研究を進めたいと考えている。講義では、その一端を提示・紹介し、またくずし字で書かれた古文書の読解も行っている。演習では、都道府県域など、ある一定の地域をとりあげ、そこに残された史料を用いて、史料批判や読解、論点の発見や展開の方法などについて議論している。著書に『近世の土地制度と在地社会』(東京大学出版会)がある。
高橋 典幸は、中世史を専攻している。武家政権の組織、とくに鎌倉幕府の御家人制に注目し、軍事制度の側面からその特質にアプローチしているが、近年は、社会的・地域的側面にも関心を向け、続く室町幕府の成立過程・特質も検討課題としている。著書に『鎌倉幕府軍制と御家人制』(吉川弘文館)、『源頼朝』(山川出版社)、『日本軍事史』(共著、吉川弘文館)などがある。講義では、その成果もふまえて武家社会について広く論じ、かつ古文書学についても概説する。演習では鎌倉幕府の歴史書である『吾妻鏡』を講読し、史料読解の基礎の習得をめざす。
また、以上の専任教員以外にも、史料編纂所や他学部・他大学の教員の方を非常勤講師として招き、特徴ある魅力的な講義や演習を開講していただいている。
(3)研究室と史料編纂所
研究室は、法文2号館の1-4階に「散在」しているが、その中核は1階東南の隅にある。ここには助教・副手がおり、また学生・大学院生から教員まで、全構成員の「溜まり場」ともなっている。研究室は狭いながらもきわめて開放的であり、教員はもちろん、助教や先輩の大学院生から懇切な指導や助言を受けることができる。
研究室図書は、日本を代表する規模の日本史関係図書を所蔵するが、1・2・4階研究室や文学部図書室・文学部3号館図書室などに分散配置されており、求める時代・分野の図書のありかを知るには多少の「慣れ」が必要である。
授業以外にも、ゼミ旅行や史料調査、卒論合宿、各種の研究会・勉強会などが活発に行なわれており、これらを介して多様な学習の機会を得ることができる。研究室全体の行事としては、4月の進学生歓迎会、5月の所蔵図書総点検(インスペクション)、2月の卒業論文口述試験後の予餞会などがある。
研究室メンバーの研究成果を発表する媒体として、史料の調査・研究を中心とする論文・翻刻・解説などで構成される『東京大学日本史学研究室紀要』(年1回刊)と、博士論文(甲種)を簡易出版する『東京大学日本史学研究叢書』とが、研究室の編集により刊行されている。また、研究室による史料調査の成果をまとめて、『現状記録調査報告書』のかたちで刊行している。
当研究室と歴史的に関係の深い部局として、東京大学史料編纂所がある。史料編纂所は、『大日本史料』『大日本古文書』などの史料集の編纂事業や広範な史料情報の集積・再編成・公開事業を行なっている機関で、古代から近代初頭に至る膨大な史料を原本・影写本・写真版その他の形で所蔵している。当研究室の学生は、所定の手続きに従い、これらの史料を閲覧することができる。同所はまた、多くの優れた日本史研究者を擁しており、当研究室の教員と相談の上で、同所の教員から指導を仰ぐこともできる。
(4)進学から卒業まで
本研究室は、文学部での専門教育への導入として、教養学部3・4学期に「日本史学研究入門」という講義二つを毎年開いている。日本史学への進学希望者は、ぜひ受講して欲しい。
3年に進学すると、高度の専門教育を受けることになる。はじめから時代や分野を狭く限定せずに、他専攻の講義を受けたり複数のゼミに参加したりするなど、できるだけ幅広い学習の場をもつよう心がけてほしい。4年次には卒業論文作成に多くのエネルギーを投入することになるので、3年の間に多くの単位を取得しておくとよい。
4年になると、卒業論文の作成が最重要課題となる。例年5月に研究室の卒論相談会が開かれ、このころを目途に専攻分野やテーマを確定し、研究計画を作成することになる。研究テーマの選定にあたっては、日本史学の範囲内であれば各自の自由が尊重される。演習などで日ごろから教員や先輩に接触して学習を積み重ねていけば、それほど無理なく自分のテーマを見つけることができよう。
卒論研究は、ほとんどの学生にとってはじめての、そしてもしかしたら人生において一度限りの、学術論文作成の機会となる。日本の歴史に埋もれた無限といってもよい研究対象と格闘し、先行研究との対話をくりかえし、自分だけの固有の論点を発見し、それを説得力ある論文に結晶させることができるかどうかが、そこでは試される。こうした経験は、卒業後すぐ就職して社会に巣立つ学生にとっても、かけがえのない財産になるはずである。
卒業後も専門研究を続けたい学生は、試験を経て大学院に入学し、研究者や専門家への途をめざすことになる。例年、卒業生の過半は就職の途を選ぶ。就職先は多様であり、文学部全体の傾向と変わらない。
▲ このページのTOPへ
イスラム学専修課程へ戻る / 文学部トップへ戻る / 東洋史学専修課程へ
|