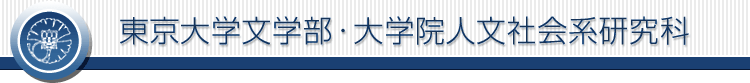|
考古学専修課程へ戻る / 文学部トップへ戻る / 言語学専修課程へ
美術史学
美術史学は、世界諸地域の古代から現代に及ぶ種々の造形を対象とする歴史学です。1889年(明治22)、「審美学」の講義題目が「審美学美術史」と改められたのが、東京大学の講義における「美術史」の名称の初登場のようです。1914年(大正3)に文学部の専修学科のひとつ「美学」に美術史の講座が設置され、3年後には学科名も「美学美術史」と改称されたといいますから、講座の創設は日本の中では東京藝術大学に次いで古いことになります。1963年(昭和38)には「美術史学」が独立した専修課程となり、1968年(昭和43)にはそれまでの思想関係の第一類から歴史関係の第二類へと移行しました。そして歴史文化学科の中の一専修課程として現在に至ります。
こういう機構の変遷は、ある程度この学問の性格を物語ってもいます。つまり、美術史学はまず美や藝術について考える学問の中に生まれ、しかししだいに美学とは異なる領域を形成し、歴史学の一分野を志向するようになったわけです。美術史学の主要な課題は、現に存在する作品を緻密に調査分析して、美術の歴史的展開を具体的に明らかにすることです。そういう点では考古学や文学史に近い研究態度を有しています。もちろん文献史料をもとに、遺品のない時代や作者の伝記、美術をめぐる制度や流通などについて考察もするのですが、その場合でも求められる実証性が、この学問を<イメージの歴史学>へと向かわせたといえるでしょう。根拠のない評論めいた独白は、ここでは歓迎されません。自分ではなく作られた物の立場に立って、現在ではなくそれが生まれた状況にもどって考えるのが重要です。とはいっても、ある程度具体的・実証的でありさえすればあとはかなりの自由を研究者に認める鷹揚さも美術史学にはあって、それが学問なり研究室の闊達な雰囲気に結びついているようです。
|

美術史学研究室における懇親会
|
進学を迷う学生さんによく尋ねられる質問のひとつは、美学芸術学とはどう違うのですかというものです。某大学の先生は同種の質問に「美学は暗い、美術史は明るい!」と答えたそうですが、当たっているかどうか。勉強の好きな人が美学を選んでいる傾向は感じますけれど。もとはひとつの学科だったのですから、どちらでも美術の研究はできます。ただ、美術史が造形そのもののありようから眼を離すことなく考え続けようとするのは、哲学系の学問とは違う点でしょう。美について思索するよりも前に美術品をながめること自体が快楽だという人に向くようです。もうひとついえば、美学の授業内容が概ねヨーロッパとそれに関連する事象であるのに対して、美術史ではヨーロッパと同等かそれ以上に日本・中国・イスラーム関係の授業が充実しています。西洋美術に偏らないのは日本の大学の利点で、名乗るまでもなく比較文化研究の要素を備えています。
2年生の4学期に開講される「史学概論」は、歴史文化学科共通の必修科目です。ほかに哲学・美学の講義4単位と歴史学・考古学4単位が必修になっているのは、この学問の成り立ちゆえです。美術史学専修課程の科目は講義16単位、演習8単位、卒業論文のみを必修としていますが、専任の教員以外にも学内学外の教員の協力を仰ぎ、幅広い内容の授業を用意していますので、できるだけ多くの授業に出席することを勧めます。教育の目的のひとつには、西洋・東洋・日本の美術史に関する広い知識を得ると同時に、美術作品の質の判断力を身につけ、調査と考察の方法を理解するということがあります。進学した3年生は、通常は5月に行なわれる関西見学旅行の演習に参加して、実物を楽しみ、よく観察し、それについて調べ考えるという美術史学の基本に触れることになります(この旅行ゼミでは、台湾や韓国に出かけたこともあります)。日常の授業でも首都圏の博物館・美術館・美術商を見学したり、スライド・写真を多用して、眼の記憶と感受性を豊かにすることが配慮されています。演習は特に、外国語や古典語を中心とした文献史料の正確な読解力を体得すること、さらには学問的な手続きに則りながら独創的な研究を行ない、自らの研究成果を発表する能力を養うことを目的としています。研鑚の成果が卒業論文です。テーマは、教員の専門と無関係に学生が自由に選択し、ギリシャ彫刻から20世紀の写真まで、きわめて多彩です。
学部卒業で就職する学生は、出版・放送など、直接に美術史学とは関係のない職を得るのが普通です(まれに学部卒で美術館学芸員になる人もいます)。専門家を目指す人は大学院に進学し、修士課程を修了した時点で、あるいは博士課程在籍中に、多くは全国各地の美術館・博物館に学芸員として就職しています(博士論文を書いて大学に職を得る人や、新聞・雑誌の美術記者になる人もいます)。進学のためには、西洋・東洋・日本の美術史に関する専門科目と外国語2か国語の筆記試験にパスした上で、卒業論文をもとにした口述試験に合格する必要があります。熱意のこもった卒論を書くことがだいじです。学芸員資格を得るための単位も取っておくべきです。なお、日本人の大学院生が外国に留学する一方で、外国から日本美術や中国美術を勉強しに来日する留学生も常にいて、ときには外国人研究者を招いて講演会も行なわれるなど、研究室の国際交流は活発です。
|

小佐野教授の講義。画像を使用した授業で視覚情報の処理能力を鍛える。
|
|

旅行ゼミ 浄土寺にて
|
美術史学は大学の中でのみ生きている学問ではありません。社会との密接な関わりを持ちます。それゆえ教員は、国・地方公共団体・私立の美術館・博物館の運営評議員や作品購入に関する委員となったり、一般の観客に向けた講演を行なうことも多くあります。国宝・重要文化財の指定・保存に関する審議会の委員や、老舗の東洋美術史研究誌『国華』の編集委員も歴代の教授が務めています。大学院生は美術館などでアルバイトをするほか、近年は授業の一環として美術館の特別展のカタログ制作を手伝うこともありました。
かつて東京大学で美術史を学んだ研究者たちは、西洋・東洋・日本の古代から近代まで、絵画・彫刻・工芸のほとんどあらゆる分野で、日本における美術史学の発展に主導的な役割を果たし、国際的に高い評価も得てきました。活躍の場は大学・研究所・博物館・美術館・官庁・ジャーナリズムと多岐に亘ります。これからも意欲ある方が美術史学に加わり、造形の息づく現場に立ち会い、イメージについての具体的な思考を深める仕事をしてもらいたいと思います。
|

東京大学美術史学研究室所蔵「探幽縮図」より「布袋図」
|
|

2013年研究室主催国際シンポジウム「SEN : On Lines and Non-Lines」
|
▲ このページのTOPへ
考古学専修課程へ戻る / 文学部トップへ戻る / 言語学専修課程へ
|