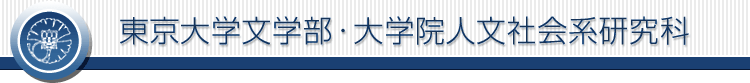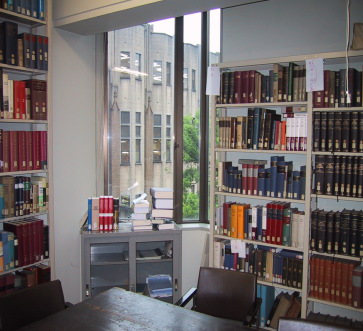|
英語英米文学専修課程へ戻る / 文学部トップへ戻る / フランス語フランス文学専修課程へ
ドイツ語ドイツ文学
|
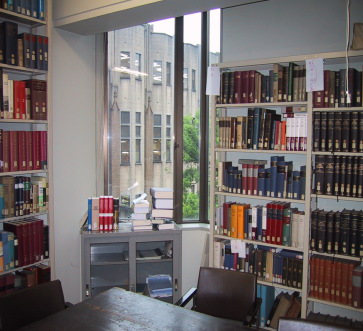
(研究室辞書室 窓の外は総合図書館)
|
(1)独文研究室について
独文研究室は、文学部3号館4階、東に三四郎池を見おろし、西に総合図書館前広場を見渡す位置にあって、四季の移ろいと一日の時の流れを鮮やかに感じることができます。ここでの学生生活は、ときには木洩れ日を浴びながらゆったりと、ときには激しく自己の内部の時間と対峙しながら営まれることになるでしょう。
一番大きな中央の部屋が助手室あるいは助教室、つまり研究室のジェネラル・マネージャーの室で、コーヒー・紅茶・緑茶等も用意されていて、いつも学生や教員が出入りし、研究室全体の談話室ともなっています。そのほかに、ゼミ室、辞書室(兼自習室)、学生室、教員室があります。助教室と辞書室には共用パソコンが置かれ、ゼミ室にはビデオ・オーディオ装置もあって、リートやオペラ、演劇、映画等の鑑賞会場にも、また、コンパ会場にも化けます。
(2)ドイツ語とドイツ文学について
ドイツ語のあり方をわたしたちの日本語と比べるとき、言語構造以前に目につくのは、英語などとはまた違った意味で国境を越えた言語だということでしょう。国があって国語がある、あるいは、ひとつの言語を使う集団がまとまってひとつの国家を作ってきた、というのではなくて、この言語は中央ヨーロッパの広い地域で使われてき、現在はそれが、おもにドイツ、オーストリア、スイス(の大きな部分)に集中している、ということなのです。日常的に使用しているという意味のドイツ語人口は、現在、およそ1億人をかぞえますが、とくに東欧でドイツ語を理解する人は少なくなく、歴史的なドイツ語文化圏・文学圏となると、さらに大きく広がります。また、汎ヨーロッパ的な移動・移住の歴史も手伝って、ドイツ文学史に登場する詩人・作家・批評家には、ユダヤ系はもちろん、フランス系、イタリア系、スラブ系の名も多く見出されるのです。
ドイツ語・ドイツ文学の歴史は、ゲルマン大移動後、カール大帝の帝国がまもなく成立する時期にあたる、8世紀半ばの古期ドイツ語の成立をもって始まるとされています。日本では奈良時代のことです。そして12~13世紀、日本でも武家文化が始まったころ、ドイツ文学は騎士文化の一翼を担って最初の隆盛期を迎えます。それから16~17世紀にはルターの聖書翻訳を大きな契機とする新高ドイツ語(近現代ドイツ語)の成立を見、それを言語上の基礎として1800年前後(ゲーテやロマン派の時代)に近代前期の、また、モデルネ期(19世紀末からの約40年)に近代後期の、多様な文学が咲き誇る時代を迎えます。それに続く狂乱の十数年は文学状況にも暗い影を投げかけ、多くの文学者が国外に逃れることにもなりましたが、20世紀後半、分裂国家の状況を背景に東西それぞれに新しい文学が生まれ、さらに20世紀末の再統一を経て、ベルリンに象徴されるように、東西対立とその解消した時代の問題をいわば最前線で経験しているドイツの文学は、現代の状況を集中的に体現しているもののひとつとも言えるでしょう。
ドイツ語といえば、「カタイ」とか、「格変化が面倒だ」とか、の声をよく耳にしますが、ひとつの言語が広がっている空間は、そうした表面的な印象でまとめてしまえるほど狭いものではありません。グリム童話もエンデの作品もドイツ語で書かれています。ドイツ歌曲の詩も、『ファウスト』も、ホーフマンスタールの流麗な文章も、ドイツ語が紡ぎ出したものです。どの言語も、その言語独自の構造を、メロディーとリズムを、美しさと緻密さを、柔らかさと硬度をもっています。ドイツ語も例外ではありません。そしてドイツ語にも、ドイツ語特有の思考形式と、言語としての全体性が宿っているのです。日本語と比べた場合、概念性が際だつ一方、その概念性もとても具象的なイメージとつながっており、それが概念性を、つかみやすい、生き生きとしたものにしていることは、もうこれまで学ぶ中で気づいている諸君も多いことでしょう。母語と英語以外に今ひとつ、異質な言語を獲得することは、とても知的刺激に満ち、かつ、自己を相対化しながら広げてゆくのにきわめて有効なことでしょう。
(3)専任教員の紹介
現在の専任教員を簡単に紹介すればつぎのとおりです。
松浦教授 : 中近世語学文学担当。ルターを本来の研究対象とし、同時に、中世文学(とりわけ叙事詩と神秘思想など)を研究。ファウスト素材に関する翻訳と解説もある。
重藤教授 : ドイツ語学担当。文法理論(とりわけ統語論と意味論)に基づく現代ドイツ語の分析、およびドイツ語の歴史的変化の記述を、主たる研究対象としている。
大宮教授 : 近現代文学担当。19世紀末から20世紀の文芸と思想の関わりを、ベンヤミン、エルンスト・ユンガー、ハイデガー、アーレントなどを結節点にして考えている。
宮田准教授 : 近現代文学担当。ノヴァーリスをひとつの中心として、現代の文芸理論も参照しつつ、<ロマン主義>がはらむさまざまな問題と可能性を、その前史と後史のなかに探ろうとしている。
KEPPLER-TASAKI准教授 : 近現代文学担当。ゲーテを研究の中心としながら、近世から現代に至るドイツ近現代文学を、祈り・中世・映画という諸領域との関わりで捉えようとする研究を精力的に進めている。
そのほか、毎年数名の非常勤講師の担当する授業があります。
(4)卒業論文および卒業後の進路について
ドイツ語ドイツ文学専修課程を卒業するには、卒業論文を書かねばなりません。日本語の本文にドイツ語の要約を付します(逆でもかまいません)。ときに卒論を嫌がる学生もいるようですが、独文の学生のなかには、そういう人はほとんど見かけません。卒業後、たとえドイツ語が直接には役立たないところに職を得るとしても、ある程度息の長さを必要とする卒論という形で読みと考えをまとめることは、人生において大きな節目を刻むことになります。参考のために、最近の卒論タイトルを少し下に掲げておきました。
卒業後の進路は他研究室と同じく、大きく分けて、すぐに就職する人たちと大学院へ進む人たちに分かれます。就職先は出版・ジャーナリズム関係、コンピューター関係、銀行や商社、公務員ないし教員等、さまざまです。
|
|
「
|
『ラトノー砦の狂える傷病兵』における誤解と機能いて」
|
|
「
|
ドイツ語の与格と日本語の「に」」
|
|
「
|
『ニーベルンゲンの歌』歌章名の研究」
|
|
「
|
カフカ『判決』翻訳に見る境界性-自我、父、神」
|
|
「
|
イルゼ・アイヒンガーの『狼と七匹の子ヤギ』について」
|
|
「
|
普遍と特殊の重なるところ -ゲーテにおける自然と学び-」
|
|
「
|
文字の機能とドイツ語正書法」
|
|
「
|
ドイツ語の接頭辞 un- を付加する形容詞について」
|
|
「
|
ハインリヒ・ハイネの『帰郷』における抒情詩の問題について」
|
|
「
|
Martin Heckmanns: “Kommt ein Mann zur
Welt“ における人間観」
|
|
|
|
|
(5)その他
もっと詳しく知りたい人は、本郷のドイツ文学研究室を気軽に訪ねてください。学部生や院生、教務補佐の人たち、あるいは教員がよろこんで相談に乗ってくれるはずです。
「学生から 1」
「・・・・・・この写生図を見てとても嬉しく思った。こんなに多種多様な
美しいものを沢山集めている人は、決して平凡で空虚なつまらないもの
を作ることはあるまい。もしこのようなものを受入れる精神を持っていれ
ば必ず正しく応用して、高貴で純粋なものしか作らないだろう。・・・・・・」
シュティフター『晩夏』(ちくま文庫、2004)
東大には名所が数多くありますが、中でも「名勝」という表現に堪えるものは三四郎池を除いて他にないものと思います。その名が漱石の『三四郎』にちなんだ命名ということは今更言うまでもないことで、場所と物語の強い結びつきを感じることが出来るエピソードだと思います。三四郎の恋や学びの空間、すなわち成長の場であった本郷。いまなお、非常に閑静で美しいところです。
独文の研究室は、まさにその三四郎池の側近く、文学部3号館に所蔵しています。本郷の施設としては随分新しい部類で、とりわけ地下の図書室は居心地よく整備されています。
独文に進んで以来常に思うのは「なんて贅沢なんだろう」ということ。蓄積された学知、歴史、蔵書に学友と、あらゆる点で無比無類の環境にいて、「しかしまあもうちょっと自分も努力すべきだな」などと自戒しつつ、次の日には趣味の本を読み漁っていたりします。贅沢といっても、この方向性は全く褒められたものではありませんが、非常に居心地のよいところであることだけは確かです。
図書室にある数多の蔵書。これを談話室「布文館」で池の面を眺めながら読書する贅沢。あるいは「趣味」を同じくする人々に出会ったこと。山手に穏やかに流れる時間・・・ そういった全てのことが、本郷・独文という場所で私が巡り合った幸運です。いい場所でいい人たちに出会ったものだと思います。
そこで終わらず、三四郎のようにすくすく「成長」出来ていれば満点なのですが。
成長というキーワードを考えると、ドイツ文学には教養小説があります。これはドイツ文学で何世紀にも渡って育まれてきた形式の1つで、主人公が遍歴や修行を通じて成長していく様を描くものです。『三四郎』にもそのような側面はありますが、冒頭では「本場」の教養小説として『晩夏』を引いています。
『晩夏』の内容を簡単に紹介するならば、延々と繰り返される氏名不詳の青年と「薔薇の館」の老主人が繰り返す教育的な対話、穏やかに流れる時間、美しき令嬢ナターリエへのまなざし、深まる家族への理解と愛情、等々。主人公の成長はあまりに遅く、加えてまったく変哲のないストーリー。全てが終わる前に厭きてしまって、文庫本を投げ出す読者が多い物語です。しかしそれでも、館の主人の熱意は衰えることがありません。青年の可能性に全幅の信頼を置いて、ひたすら成長を待ち続けているのです。青年の熟成に必要なものは全て与えられており、老主人が作り出した「薔薇の館」に備えられた数多くの芸術的作品群が青年の心を大いに高めていきます。そうした完璧な環境はあたかも、青年の到来を見越して準備されていたかのよう・・・
青年の幸運な出会いを知った父は、冒頭の言葉で館の主人を称えます。さらに、趣味と教養に注力する「時間と財力と協力者を持つのは、めったにない幸運」だと青年に伝えます。
優れた教師のもとで「多種多様な美しいもの」を学ぶことが出来るならば、恵まれた境遇で育つという「めったにない幸運」に十分応えたと言えるでしょう。それも、自ら産出するための土台として学び取ったならば格別。
「そのうちに、あの方の御好意に応じて、幾枚か写せるような時が、私にも遅ればせながら恵まれるかもしれない。そうなれば、私の晩年にも相当の値打が加わるというものだ。」
多くの人が、価値ある場所と出会いを選択なさいますように。
「学生から 2」
Rose, oh reiner Widerspruch, Lust,
Niemandes Schlaf zu sein unter soviel
Lidern
ばら、なんと純粋な矛盾、そして喜び
あまた瞼の下で 不在のもの の眠りで
在ることの
扉を開けると淹れたてのコーヒーの匂い。それから暖房の効いた部屋の柔らかな空気。とくに冬の晴れた日の文学部3号館4階は心地よい。助教室でクッキーをこっそり頂いて、クリープ入りの濃いコーヒーを片手にゼミ室へと向かう。まだ授業は始まっていない。陽の光がぽかぽかと差していて、窓の外に三四郎池横のケヤキの樹を眺める。ひっそりとした雰囲気。これからはじまることへの微かな予感。授業前の教室はいつも、ひとりでいると、毎日来ているところなのにそわそわする。
ドイツ文学の研究といっていったいなにをするのか、と思う人は多いかもしれない。私自身、実際に入ってみるまでは正直よく分からなかった。1年前、とにかくしどろもどろのドイツ語を携え、何もわからないまま飛び込んだこの世界は、当初私が想像していたものよりはるかに深く、広いものだった。日々ドイツ語の文献とにらめっこをし、ひとつの文章で何度も何度も辞書を引く。ときにはその文章の謎かけに、ごはんを食べているときもお風呂に入っているときも布団に入ってからも四六時中頭をひねり、ふとした瞬間の閃きからその謎かけに、それが書かれた瞬間の作者の顔が見えたときの快感。私はどんどんとそうした快感のとりこになっていった。本郷に来て一番はじめにそんな風に出会った詩人はリルケだった。彼のとても短いひとつの声に、私はすっかり捉えられ、辞書を引いては頭を悩ませ、彼について少しでも知ろうと、年表を作ってみたり、彼の肖像画を穴が開くほど見つめてみたり、そしてバラ園にバラまで見に行った。いろいろなことを試してみても、底なし沼にはまっていき、彼の顔は、ちらとでも見えたかと思うとまたすぐに曇って見えなくなってしまうのだった。リルケの墓標に彫られたそのたった3行の言葉、そのたった3行にほぼ1年経った今でも私はまだ頭を抱えている。ふとしたときに思い出しては彼の顔を何とか見ようと頭をひねる。彼以外にこの1年間に出会った詩人・作家は10を超える。底なし沼もその数だけ私の中に現れて、ときにはそのお互いが影響しあいながら私を苦しませ興奮させ、そうしていまもそのひとつひとつが私の中でどんどんと拡がっている。
ドイツ文学の研究とはいったいなにをするのか。正直今でも私はよく分からないのかもしれない。しかし、それでも私は、微かにしかし文字によってくっきりと残された誰かの声が、私の生きている今という瞬間とその声の時間とを繋ぐような、そうしてその瞬間に感じる興奮と快感、その興奮と快感から自分の中で何かが動いて変わっていくような、そういう世界の拡がりを求めているのかもしれない。そうして今日も私は3号館の階段をのぼっている。私の中にできたいくつもの底なし沼へ向かって。
「学生から 3」
いつ、どこで、誰が、いったい何のために"Deutsch"を「独逸」と表記することに決めたのか不勉強にして知らないが、「独文」という略称はいかがなものかと思う。第一、「独」の一文字だけでもう逃げ出しちゃいたいくらい濃厚に重厚でシリアスでブルースな印象だ。「死」や「破滅」とかいう日常的にはあまり関わりたくない言葉と並んで、「孤独」が「文学」の言説で褒め言葉になってしまうことは確かに珍しくないが、だからといって名前でわざわざ「独り」を強調することもあるまいに。「独文生」と名乗るだけでなんだかとっても孤独になった気分だ。せめて愛称くらいもっと親しみやすくて華やかなものにすればいいのに(別に「独り」が華やかでないと言いたいわけではないですが。むしろある意味で非常に華やかでエレガントなことだと思います)。そして「独文に所属する」という、この滑稽なパラドックス。「独り」の人によって構成される組織としての「独文」。このきまりのわるさといったら!最初にこの略称を考えた人の悪意はいかほどのものか。
で冗談はともかく(笑)、「独文」に進学した人が何をすることになるかというと、ドイツ語のテクストを「独り」で読み、それについて「独り」で考え、それをもとに「独り」でレポートや論文を書く、ということです(もちろん先生や他の学生に相談はできますが)。そのためには、ドイツ語で本を読めるようになるための、ウンザリするようなトレーニングを授業内外で課せられることになります。一ページに何十回も辞書を引きながら、何が何だかよくわからないようなことが書いてあるテクストを、何が何だかよくわからないような思いを抱きながら読み進めていく。でもそれがなんとなく楽しい。なぜかはよくわからないけど。という苦痛と快楽のマゾヒスティックな弁証法の極致を、「独文生」は否応無しに体験させられることになります。
幸いなことに、「独文生」たちはその名前ほど孤独でもシリアスでもありません(そうだったら困る・笑)。喫茶店でコーヒーを片手に文学談義…なんてことは全然なく(あったら困る・笑)、空き時間に何とはなしに皆して研究室に集まってジャンクフードをつまみながら昨日観たバラエティー番組のギャグをゲラゲラ笑いながら再現しあう、というひどく俗物的で健全なことを…と言いたいところですが残念ながらそういうわけでもなく(笑)、この二つの中間のようなことが日々「独文」研究室では行われています。
要は何が言いたいかというと、「独文」、悪いところじゃないよ、ということです。
▲ このページのTOPへ
英語英米文学専修課程へ戻る / 文学部トップへ戻る / フランス語フランス文学専修課程へ
|