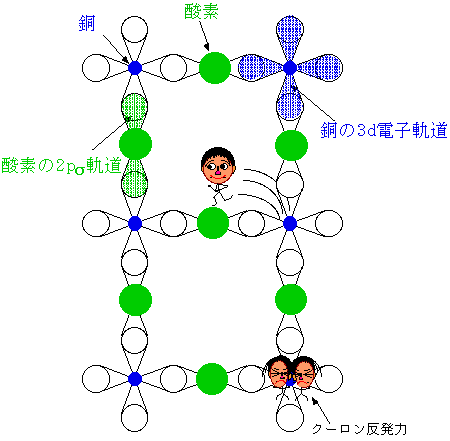今田研究室ホームページへ
 この章の最初にもどる 前のページ
この章の最初にもどる 前のページ 次のページ
次のページ
 電子間のクーロン相互作用の効果が重要な、強相関電子系
電子間のクーロン相互作用の効果が重要な、強相関電子系
電気伝導の舞台 ---量子力学に従う電子の運動
原子では、原子核のまわりに1s, 2p, 3dといった名前の軌道ができており、電子はその軌道上で原子の周りを回っている。古典的な系と違って、電子の運動は、量子力学の法則に従う。このため、原子の周りをまわっている電子の運動には1s,2pと言うような名前のとびとびの軌道しか許されていない。この軌道の出来方が量子力学によって説明できる。次に、孤立した原子ではなくて、原子が周期的に並んだ金属結晶中の場合を考えよう。この場合は、1つの原子の周りにできた電子軌道をまわっている電子が、ときどき(あるいは頻繁に)隣の原子の軌道に飛び移って、あちらこちら遠くまで出かけるようになる(そして元の場所にほとんど戻ってこない)。我々は金属中で電流が流れることを知っているが、この電流は、今説明したようにして、原子から原子へと電子が動くことによって生ずる。このように飛び回ってさまよっている電子を遍歴電子、一つの原子の軌道にじっとしている電子を局在電子という。また電子は動き回りながら、お互いにクーロン相互作用をしているので、お互い避け合って動き、複雑な運動をする。
高温超伝導体の場合
そこで、高温超伝導体の場合について説明しよう。高温超伝導体には銅が必ず含まれる。電子は銅原子のまわりの3d軌道と呼ばれる電子軌道から途中の酸素の2p軌道を経由しながら、隣の銅原子の3d軌道へと跳び移り、下図のように結晶中を動き回っていると考えられている。この跳び回っている遍歴電子を伝導電子とも呼ぶが、伝導電子の数は銅原子一個あたり、だいたい1個程度である。この銅から銅へと飛び回っている電子の場合は特にお互いのクーロン相互作用の効果が大きい。その理由を説明しよう。
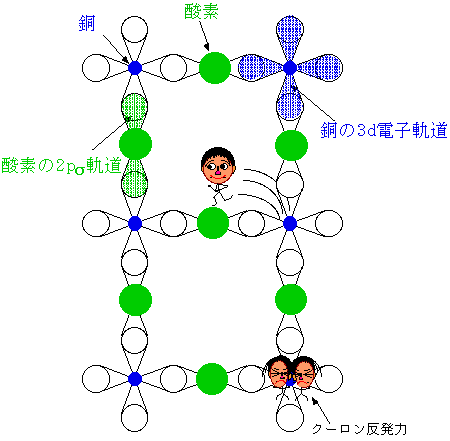
銅酸化物高温超伝導体の電気伝導は銅の3d軌道と酸素の2p軌道からなる ネットワークが担っている。電子()は銅の3d軌道の間を酸素の2p軌道を経由しながら跳び回って、同じ銅サイトに2つ電子がいると大きなクーロン反発エネルギーの損があり、なるべく避けあいながら動こうとするため電子間相互作用の効果が大きい。
銅原子は遷移金属元素と呼ばれる元素の1つであるが、ほかの遷移金属元素の場合と同じように、伝導電子のいる銅原子の3d軌道の大きさは、銅原子間の距離に比べて小さいことが知られている。つまり原子の周りの小さな軌道に身を寄せていてあまり外を飛び回りたがらない(つまり局在性が強いとも言う)。銅原子間の距離が大きいので電子の跳び移りの頻繁さ(つまり遍歴性)を表わす運動エネルギーは小さくなり、一方3d軌道の広がりが小さいので同じ銅原子サイトに2つの伝導電子がいるときに感じるクーロン斥力エネルギーが相対的に大きい。クーロン斥力エネルギーは距離に反比例するから、同じ狭い軌道に閉じこもっている電子同士に働く斥力は強くなるからである。特に高温超伝導体のすぐ近くの物質であるLa2CuO4のように、銅原子あたり伝導電子の数がちょうど1つのときには、モット絶縁体と呼ばれる絶縁体となる(A-2-5とB-3-2を参照)。電子同士が同じ軌道にいたがらないので、ひしめきあって動けなくなってしまうのである。クーロン相互作用がないときには金属のはずなので、クーロン相互作用のために電子が動けなくなるというドラマチックな効果である。ところが、ブロック層にあるランタン(La)のかわりにバリウム(Ba)やストロンチウム(Sr)を少しドープ(置き換え)すると、もともとプラスに荷電していたブロック層の電荷が減少し、逆にCuO2面にプラスの電荷を供給する。このためCuO2伝導電子の数が減り、電子が少しは動き回れるようになる。これをドープされたモット絶縁体と呼ぶ。このドープされたモット絶縁体の低温で超伝導が生ずる。だが、超伝導が生じているような電子濃度では電子は依然としてひしめきあっており、電子間クーロン反発相互作用の効果が大きい。電子間クーロン反発相互作用の効果の大きな系を強相関電子系と呼ぶ。
高温超伝導が生じている領域をブロック層への電荷のドーピング濃度(x)と温度(T)の関数として図示すると下図のようになる。電子相関が大きくて電子がひしめきあっているためにxが小さい領域では常伝導状態で普通の金属とは異なった奇妙な振る舞いが見られ、異常金属と呼ばれたりしている。超伝導はこの異常な金属状態から温度を下げたときに実現する。電子間相互作用(電子相関)が強いこと、つまり電子がひしめきあっていることの効果を理論的に研究するために、ハバード模型やt-J模型とよばれる強相関電子系の理論模型が研究されている。
銅酸化物超伝導体に見られる相図。超伝導はモット絶縁体にキャリアを少しドープ(注入)したときに生ずる。またこの領域で超伝導転移温度よりも高い温度で普通のフェルミ液体で表わされる金属とは異なるふるまいが見られる。
高温超伝導体物質の持つ特徴のその他の項目
(クリックするとその項目に進めます)
(1)銅と酸素を含む層状物質
(3)常伝導のときの金属状態はどう奇妙なのか?
(4)超伝導もエキゾティック
(5)銅酸化物超伝導の応用の可能性
 この章の最初にもどる 前のページ
この章の最初にもどる 前のページ 次のページ
次のページ
今田研究室ホームページへ
 この章の最初にもどる
この章の最初にもどる  次のページ
次のページ![]()