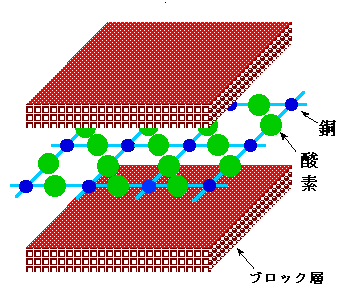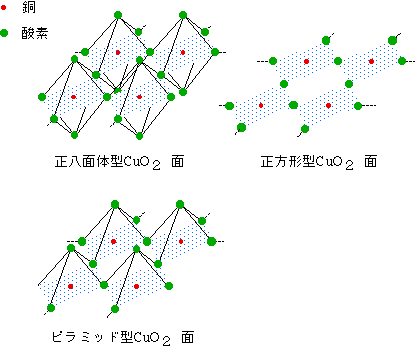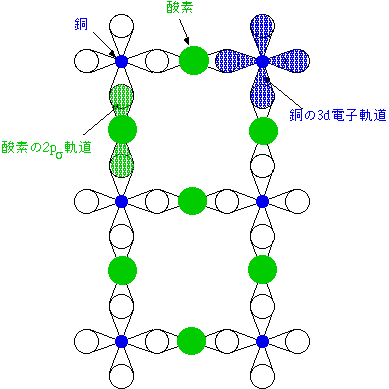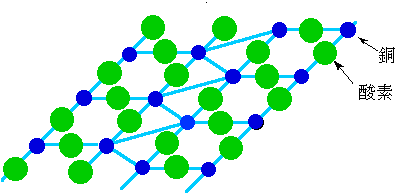面での電気伝導を通じて生じていることもほぼまちがいなく、理論模型の多くがこの2次元面を対象に考えている。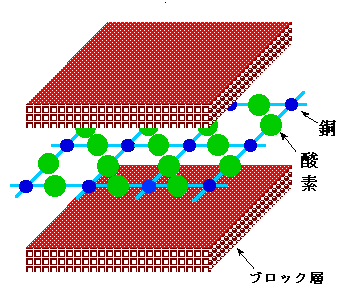
ここに述べた銅酸化物のような遷移金属酸化物の研究の歴史は古い。強相関電子系という観点からも,NiOがなぜ絶縁体となって金属にならないかという問題をモットがすでに1949年に提起していた。また上に述べた化合物のうちのかなりのものが,CuO2面といわゆる頂点酸素とをあわせて下図のような八面体構造あるいは頂点酸素の1つ欠けたピラミッド構造を単位としていることも特徴である。一方,たとえばNd-214化合物のように頂点酸素を含まず、CuO2面とブロック層だけからなる構造の場合もある。
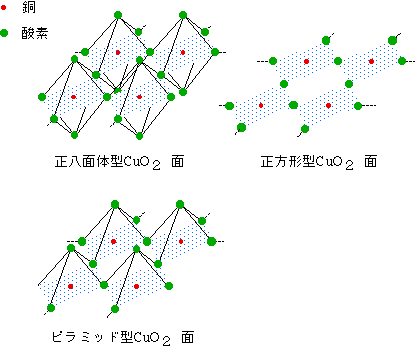
常温以下の温度での通常の金属の電子系ではフェルミエネルギー付近のエネギーを持った電子や正孔のみが励起され,電気伝導などの現象に関与している。CuO2面の電子軌道のうち、我々の問題にする常温あるいはそれ以下の温度の電気伝導、超伝導などの現象に関与しうるものは、3d遷移金属元素である銅の3d軌道と酸素の2p軌道である。そのうち、特に電気伝導を担っているのは、下の図のように銅の3dx2-y2軌道と、酸素の2 ps軌道の共有的な結合が作る正方格子のネットワークであろうと考えられる。
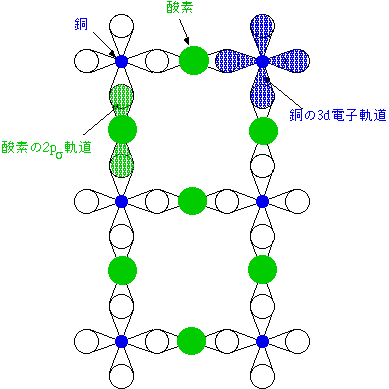
銅酸化物高温超伝導体の電気伝導を担う銅の3d軌道と酸素の2p軌道からなるネットワーク。
また最近、転移温度は10K程度と高くないが、2次元正方格子のネットワークをもったCuO2面ではなくて梯子状の形状をもった1次元的異方性があるといわれている銅酸化物(梯子物質)でも超伝導が発見された。超伝導メカニズムを解明する上でも参照物質として注目されている。
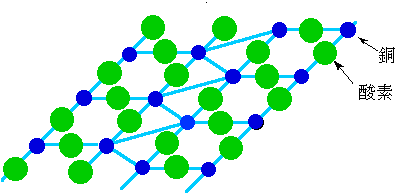
梯子状物質(スピンラダー)の梯子格子面の構造 この章の最初にもどる 前のページ
この章の最初にもどる 前のページ 次のページ
次のページ
今田研究室ホームページへ戻る
 この章の最初にもどる
この章の最初にもどる  次のページ
次のページ![]()