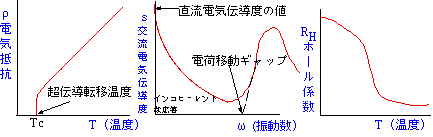今田研究室ホームページへ戻る
 この章の最初にもどる 前のページ
この章の最初にもどる 前のページ 次のページ
次のページ
 異常な常伝導金属相
異常な常伝導金属相
反強磁性相関
高温超伝導は反強磁性絶縁相に隣接して生じる。
絶縁相での反強磁性秩序状態への転移温度TNは、たとえばLa-214系で約300K(摂氏27度),Y-123系では450K(摂氏177度)に達する。さらに, TNよりもはるかに高い温度から、2次元のCuO2面内でスピンの反強磁性的な短距離相関(理論上は有限の長さの相関の存在を指す)が発達していることが中性子散乱で観測されている。
銅酸化物超伝導体のスピン相関はホールや電子のドーピングによって大きく変化する。例えばLa-214系の場合でいえば、わずかに2%程度のドーピング、すなわちドーピング濃度0.02で反強磁性秩序は消失してしまう。ドーピング濃度をふやしていくと反強磁性秩序が消失してまもなく金属絶縁体転移によって系は金属相へ転移する。反強磁性長距離秩序が消えて金属となっても、反強磁性の短距離相関は強く残り続ける(絶縁体の時と比べて反強磁性の周期がずれて、インコメンシュレートな周期の相関が残る)。これは中性子散乱実験や核磁気共鳴実験(NMR)によって明らかにされている。反強磁性相関距離のドーピング濃度依存性が中性子散乱で調べられて相関距離がほぼ平均ホール間距離であることが指摘されている。金属相は単純な金属と違ってこのような反強磁性スピン相関の強い影響を受けている。
輸送現象の異常
通常の金属すなわちフェルミ液体の示す特徴に対して、銅酸化物超伝導体の金属相の電荷ダイナミックスはどのように異常だろうか?
ここでは主に電気抵抗やホール係数などの輸送現象の異常について説明する。
まず、電気抵抗Rは、電子間相互作用が強いフェルミ液体の場合はR=R0+bT2のような形になることが予想されるが、銅酸化物超伝導体ではR=R0+bTというふるまいが非常に広い温度領域(ある場合には10K程度から1000K程度に至るまで)で見られ、かつ良質と考えられるサンプルではR0がゼロに近づくように見える。残留抵抗のR0を差し引くと、電気抵抗がこのように広範囲の温度で温度Tに比例することの原因は電子間相互作用のためであると考えられている。
このように電気抵抗が残留抵抗の部分を除いて温度に比例していることが金属状態がインコヒーレントである(悪い金属である)ことの一つの証拠である。
電気伝導度だけでなく,ホール係数RHも異常である。ホール係数は単純な1種類のキャリアーの金属ではRH=1/necとなり温度に依存しない。ただしnがキャリア濃度、eは電子の電荷、cは光速である。しかし銅酸化物高温超伝導体では複雑な温度依存性を示す。ホール係数は低温になるほど増大する傾向がある。
さらにホール係数のドーピング濃度dへの依存性も異常である。銅1サイトあたりの電子濃度nはモット絶縁体に近づくときn=1に近づき、ホールドーピングのときはn=1-dである。ところが,ホール濃度が小さいとき低温でのホール係数は温度を固定するとバンド描像の予測する1/nではなくて、おおざっぱに1/dに比例するように見え、しかも符号はキャリアがホールであることを示唆している。
電子間相互作用を考えない限り、モット絶縁体の近くでは、バンド的な描像でキャリアは電子であるはずであるから、キャリアがホールであることを示すホール係数の結果はこの描像に反する。
すなわち、ホール効果の実験結果は単純に考えるとキャリア数が少ないということを示している。これは角度分解光電子分光の実験結果と矛盾するように見える。光電子分光の結果は、キャリア数が電子間相互作用がないとしたときの値と一致しているように見える(もっと正確には、フェルミ面の大きさが大きいように見える)からである。
さらに金属的な領域で複素電気伝導度がドゥルーデ則に従わないという異常も観測されている。大ざっぱには大変高い振動数(1eV程度)まで伝導度が1/wに比例しているように見えている。これは標準的な金属の従うドルーデ則の予測が1/w2に比例することと食い違っている。
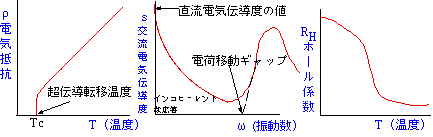
銅酸化物高温超伝導体に見られる異常なふるまいの模式図
 この章の最初にもどる 前のページ
この章の最初にもどる 前のページ 次のページ
次のページ
今田研究室ホームページへ戻る
 この章の最初にもどる
この章の最初にもどる  次のページ
次のページ![]()