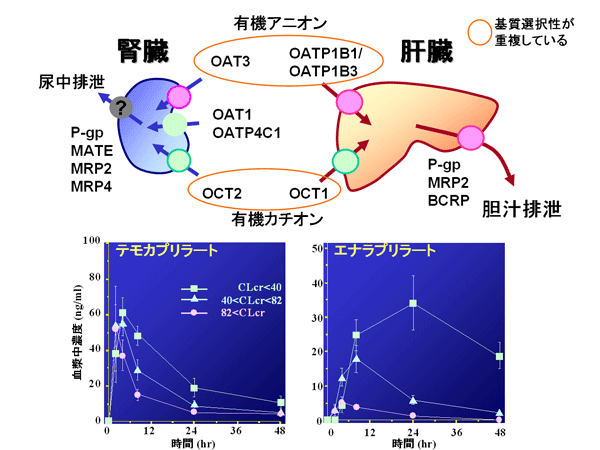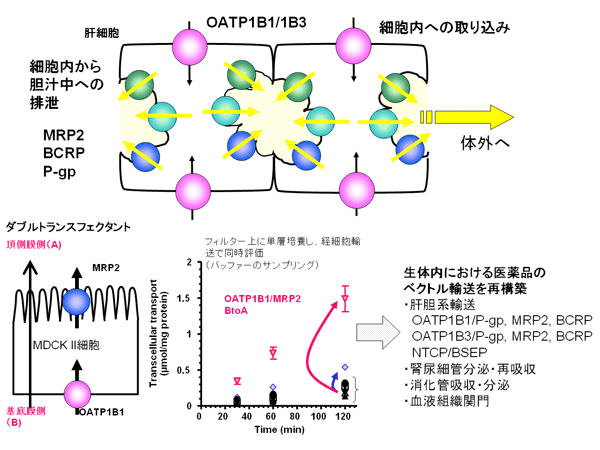| 前ページへ 次ページへ |
| 薬物分子の体内動態を解明し、安全な医薬品のデザインと医薬品適正使用に貢献する キーワード:薬物トランスポーター、遺伝子多型、薬物間相互作用、ドラッグデリバリーシステム(DDS)、ファーマコキネティクス、胆汁排泄、尿細管分泌、血液脳関門 |
|
|||||||||||||
薬物による効果や副作用を予測するためには、薬物分子の体内での動きを知ることが必須です。しかし、薬物は様々な物性を持っているために、一概にそれらの動きを説明することはできません。私たちは、これらの薬物を細胞内へ取り込んだり排出する働きを持つ、薬物トランスポーター群の性質を知ることで、薬物がどのような動態特性を示すのか予測できるのではないかと考えています。薬物速度論、生化学的および分子生物学的手法と いった様々な手法を用いて、肝臓、腎臓、小腸および脳における薬物トランスポーターの解析を行っています。また、薬物の効き方には個人差があることが知られています。上記の研究を通して、私たちはこの個人差に薬物トランスポーターが大きく関与していること、また他の薬との相互作用の原因になることも見出してきました。こうした研究は、最終的に副作用を最小限に抑え、薬効を最大限に引き出すことのできる医薬品の開発、使用法の確立につながるものであり、テーラーメード医療時代を見据えた重要な研究領域であると自負しています。 |
||||||||||||||