|
|
|
日本語日本文学(国文学)専修課程へ戻る / 文学部トップへ戻る / インド語インド文学専修課程へ
中国語中国文学
亀の甲羅や牛の骨を焼いて、神の意志を問いかけていた時代から21世紀まで、中国語ほど長い歴史を持ち、多種多様な思惟や感情を記録してきた言語は他にない。中国語中国文学専修課程が対象とするのは、この歴史のすべてである。中国文明はその周辺に、無数の多彩な文化をはぐくみ、日本・韓国・ヴェトナムでは、漢字を学んで作られた文字が、それぞれに独自の思惟や感情を綴ってきた。また中国の西方は、砂漠や大山脈によって隔てられながらも、常にインドや西アジアの大文明に向かって開かれ、多くのものを吸収した。中国語中国文学の歴史は、絶えざる文化交流の歴史でもあった。
 本専修課程には、この長い歴史を扱うにふさわしい多彩な教員が揃っている。詩経・唐詩や古典小説を専攻する教員がおり、魯迅から香港・台湾の最新の文学・映画までを、研究対象とする教員がいる。語学にも現代中国言語学を専門とする教員と、出土資料を解読し古代漢語語法を研究する教員がそれぞれ揃っている。このほか学内の他の部署からの応援を加えれば、さらに広い領域をカバーする。中文科を備えた大学の中でも、これだけ充実した陣容を持つところは多くない。学生諸君には、学部生の間に、各教員の専攻する分野をすべてひと通り学ぶこと、また専攻を決めた後も、常に中国語中国文学の歴史全体と、周辺諸文化との関連を視野に入れ、研究を進めることを求めている。 本専修課程には、この長い歴史を扱うにふさわしい多彩な教員が揃っている。詩経・唐詩や古典小説を専攻する教員がおり、魯迅から香港・台湾の最新の文学・映画までを、研究対象とする教員がいる。語学にも現代中国言語学を専門とする教員と、出土資料を解読し古代漢語語法を研究する教員がそれぞれ揃っている。このほか学内の他の部署からの応援を加えれば、さらに広い領域をカバーする。中文科を備えた大学の中でも、これだけ充実した陣容を持つところは多くない。学生諸君には、学部生の間に、各教員の専攻する分野をすべてひと通り学ぶこと、また専攻を決めた後も、常に中国語中国文学の歴史全体と、周辺諸文化との関連を視野に入れ、研究を進めることを求めている。
次に本専修課程の特色として挙げたいのは、院生・学生に外国人の多いことである。各教員が専攻する分野の講義に加え、会話・作文の授業があり、大学院生のためには中国語で論文を書くための授業が開講されている。また中国や欧米諸国からの外国人研究員(訪問学者)も、常に数名が滞在し、様々な研究に従事している。研究室では、これら外国からの客人による講演や研究報告がしばしば催され、授業や合宿にも外国人研究者の参加を迎えて、学生との交流が活発に行われている。
 現在、中国語圏からの外国人留学生も多数在学している。留学生の参加は、授業のあり方にも影響を与え、それぞれに異なる文化的背景を持った学生が自由に意見を交換しつつ、ともに学ぶ環境が実現している。日本人学生にとっては、いながらにして中国語会話が上達し、わが国とは異なる様々な見方や研究方法が学べるという点で、極めて恵まれた環境である。 現在、中国語圏からの外国人留学生も多数在学している。留学生の参加は、授業のあり方にも影響を与え、それぞれに異なる文化的背景を持った学生が自由に意見を交換しつつ、ともに学ぶ環境が実現している。日本人学生にとっては、いながらにして中国語会話が上達し、わが国とは異なる様々な見方や研究方法が学べるという点で、極めて恵まれた環境である。
留学生や外国人研究者との意思疎通のためのみならず、どの領域を学ぶにしても現代中国語の語学力・読解力は重要である。したがって本専修課程を志望する諸君は、前期課程において、現代中国語に関する基礎を身につけておくことが望ましい。古典文学の領域においても、外国の文学作品として理解することが目標となるので、漢文の履修は望ましいことであるが、その読解力だけでは不十分である。とはいえ、現代中国語を履修していない、又は履修が不十分である諸君の進学希望も尊重している。これまでにも例があるが、他の外国語を学んだ経験は、中国語中国文学を学ぶ際にも生きてくる。文学部進学後の努力に期待しつつ歓迎したい。
 必修科目には、中国語学・文学の概論概説、特殊講義、演習のほかに、卒業論文がある。論文のテーマは各人が自由に選定するが、毎年夏休みの前には、専修課程全体で、卒業論文と修士論文の構想発表会が行われている。教員のみならず先輩や学友からも、様々な意見が提出され、それをもとに構想を練り直し、執筆へと向かうのである。これは論文を書く者にとって大きな助けになるばかりでなく、参加者全員にとって、自分の専門外の領域について学ぶよい機会となっている。 必修科目には、中国語学・文学の概論概説、特殊講義、演習のほかに、卒業論文がある。論文のテーマは各人が自由に選定するが、毎年夏休みの前には、専修課程全体で、卒業論文と修士論文の構想発表会が行われている。教員のみならず先輩や学友からも、様々な意見が提出され、それをもとに構想を練り直し、執筆へと向かうのである。これは論文を書く者にとって大きな助けになるばかりでなく、参加者全員にとって、自分の専門外の領域について学ぶよい機会となっている。
勉学環境で特筆しておきたいのは、どの分野も豊富な資料を収蔵し、閲覧が容易なことである。特に古典研究に必要な文献や参考図書は、漢籍コーナーに収められ、学部生も自由に閲覧することができる。共同研究室のすぐ下の階にある漢籍コーナーの便利さは、古典文学を専攻する留学生諸君の間でも好評を博している。また共同研究室にあるパソコンからは、随時各種のデータベースを検索することができる。
卒業後の進路は研究者の道を選ぶ者が多いが、教職につく者、ジャーナリストとなる者など多様であり、近年は一般企業への就職も少なくない。本専修課程は10年前より同窓会を組織し、隔年に一度会を開いているが、その席では、多様な分野で活躍する卒業生の講演が行われる。なお進学後の生活や、就職情報については中文研究室のホームページ http://www.l.u-tokyo.ac.jp/chubun/index.html に詳しい。是非参照してほしい。
▲ このページのTOPへ
日本語日本文学(国文学)専修課程へ戻る / 文学部トップへ戻る / インド語インド文学専修課程へ
|
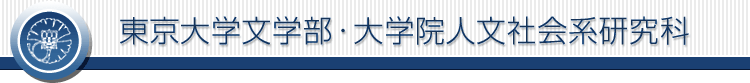
 本専修課程には、この長い歴史を扱うにふさわしい多彩な教員が揃っている。詩経・唐詩や古典小説を専攻する教員がおり、魯迅から香港・台湾の最新の文学・映画までを、研究対象とする教員がいる。語学にも現代中国言語学を専門とする教員と、出土資料を解読し古代漢語語法を研究する教員がそれぞれ揃っている。このほか学内の他の部署からの応援を加えれば、さらに広い領域をカバーする。中文科を備えた大学の中でも、これだけ充実した陣容を持つところは多くない。学生諸君には、学部生の間に、各教員の専攻する分野をすべてひと通り学ぶこと、また専攻を決めた後も、常に中国語中国文学の歴史全体と、周辺諸文化との関連を視野に入れ、研究を進めることを求めている。
本専修課程には、この長い歴史を扱うにふさわしい多彩な教員が揃っている。詩経・唐詩や古典小説を専攻する教員がおり、魯迅から香港・台湾の最新の文学・映画までを、研究対象とする教員がいる。語学にも現代中国言語学を専門とする教員と、出土資料を解読し古代漢語語法を研究する教員がそれぞれ揃っている。このほか学内の他の部署からの応援を加えれば、さらに広い領域をカバーする。中文科を備えた大学の中でも、これだけ充実した陣容を持つところは多くない。学生諸君には、学部生の間に、各教員の専攻する分野をすべてひと通り学ぶこと、また専攻を決めた後も、常に中国語中国文学の歴史全体と、周辺諸文化との関連を視野に入れ、研究を進めることを求めている。 現在、中国語圏からの外国人留学生も多数在学している。留学生の参加は、授業のあり方にも影響を与え、それぞれに異なる文化的背景を持った学生が自由に意見を交換しつつ、ともに学ぶ環境が実現している。日本人学生にとっては、いながらにして中国語会話が上達し、わが国とは異なる様々な見方や研究方法が学べるという点で、極めて恵まれた環境である。
現在、中国語圏からの外国人留学生も多数在学している。留学生の参加は、授業のあり方にも影響を与え、それぞれに異なる文化的背景を持った学生が自由に意見を交換しつつ、ともに学ぶ環境が実現している。日本人学生にとっては、いながらにして中国語会話が上達し、わが国とは異なる様々な見方や研究方法が学べるという点で、極めて恵まれた環境である。 必修科目には、中国語学・文学の概論概説、特殊講義、演習のほかに、卒業論文がある。論文のテーマは各人が自由に選定するが、毎年夏休みの前には、専修課程全体で、卒業論文と修士論文の構想発表会が行われている。教員のみならず先輩や学友からも、様々な意見が提出され、それをもとに構想を練り直し、執筆へと向かうのである。これは論文を書く者にとって大きな助けになるばかりでなく、参加者全員にとって、自分の専門外の領域について学ぶよい機会となっている。
必修科目には、中国語学・文学の概論概説、特殊講義、演習のほかに、卒業論文がある。論文のテーマは各人が自由に選定するが、毎年夏休みの前には、専修課程全体で、卒業論文と修士論文の構想発表会が行われている。教員のみならず先輩や学友からも、様々な意見が提出され、それをもとに構想を練り直し、執筆へと向かうのである。これは論文を書く者にとって大きな助けになるばかりでなく、参加者全員にとって、自分の専門外の領域について学ぶよい機会となっている。